
今回月曜日に有給を取ったことで、4連休となった。
世間的にコロナもだいぶと落ち着いてきたこともあり、約1年ぶりに実家に帰省した。
久しぶりに帰省すると、帰省先のいわゆるローカルルールというものの存在を改めて実感することがあるし、しばらく帰省していないからこその、新たな発見もあった。
やっぱりエスカレーターは右に立つ
私が帰省するたびに、帰ってきたことを実感するのがエスカレーターの立ち位置。
関東では左に立ち、関西では右に立つ。
新幹線で新大阪に降り立ち、ホームから改札に向かう際のエスカレーターの立ち位置で、まずは大阪に帰ってきたことをまず最初に実感する。
みんな関西弁
関東にいると、周りから聞こえてくる言葉は訛りやイントネーションがいわゆる標準語ばかりになる。
ところが関西は関西弁がある。
つまり周りの人から聞こえてくる言葉も関西の訛りとイントネーションとなる。
今まで関西に住んでいたときは、気にしたことがなかったが、周りから関西弁しか聞こえてこないという状況は、なかなかに不思議なもの。
当然といえば当然だけど、関西で働く店員さんも大体関西人。
そうなると、店員さんの話し方も必然的に関西弁となる。
関東での標準語に慣れてしまったのもあり、話しかけられる時に関西弁だと(お、関西弁!)と無意識に言葉を聞き逃すことができなくなってしまう。
とはいえ、私は普段から話すときは関西弁を隠していない。私と話している周りの人からしたら、(お、関西弁!)と思われていたと思う。
無意識で行きたい先の電車に乗れる。
関東に住み始めて5年以上経つが、いまだに行きたい先の電車に乗るときには、乗り換え案内がないとたどり着くことができない。
まだまだ乗ったこともない路線もあるし、知らない路線だってたくさんある。
行きたいところのなんとなくの方向すらわからないから、大体どの路線に乗ればいいのかといったことがさっぱりわからないのだ。
そして関西には20年以上住んでいた。
どうやら、なんとなくどの路線に乗ったらいいかとか、どの方角に行けばたどり着くのかといったことが体に染み付いているよう。
そのためか、新しい場所に行くとなった時も、なんとなく方向はわかるし、なんとなくどの路線に乗ればいいのかもわかる。
なんなら、どれぐらい行くのに時間がかかるかもわかってしまう。
関東に比べて、路線の数が圧倒的に少ないのもあるが、いまだに帰省するたびに、電車に乗る時は乗り換え案内を頻繁に見ないでも、行きたい先にたどり着くことができる。
やはり、長年住んでいた場所は、どれだけ時間が経っても覚えているものなのか。
梅田の地下はいつも迷路
これは私が関西に住んでいた時から思っていた。
住んでいても道に迷う、大阪の地下魔境といえば梅田。
今回久しぶりに帰省した時も、やはり道に迷いかける。
どうしてここまで、人を惑わせてしまうのか。
それは、常にどこかが工事をしていて、勝手知ったる道が塞がれてしまうからだ。
あそこの工事が終わったら、次はここを工事。その次には、ここを工事。次はここ。次はここ。次h‥。
といったように、一気に工事をしないので、何年もかけていろんなところが常に工事をしている状況になる。
しかも工事が終わると、前まであった店や目立つ待ち合わせ場所の目印となるようなものも変わってしまう。そうすると、一から道や店を覚えなければならない。
こんな感じで、街並みというのは常に進化を遂げているのだ。
また次の帰省の時はどのように変わっているのか楽しみになってくる。

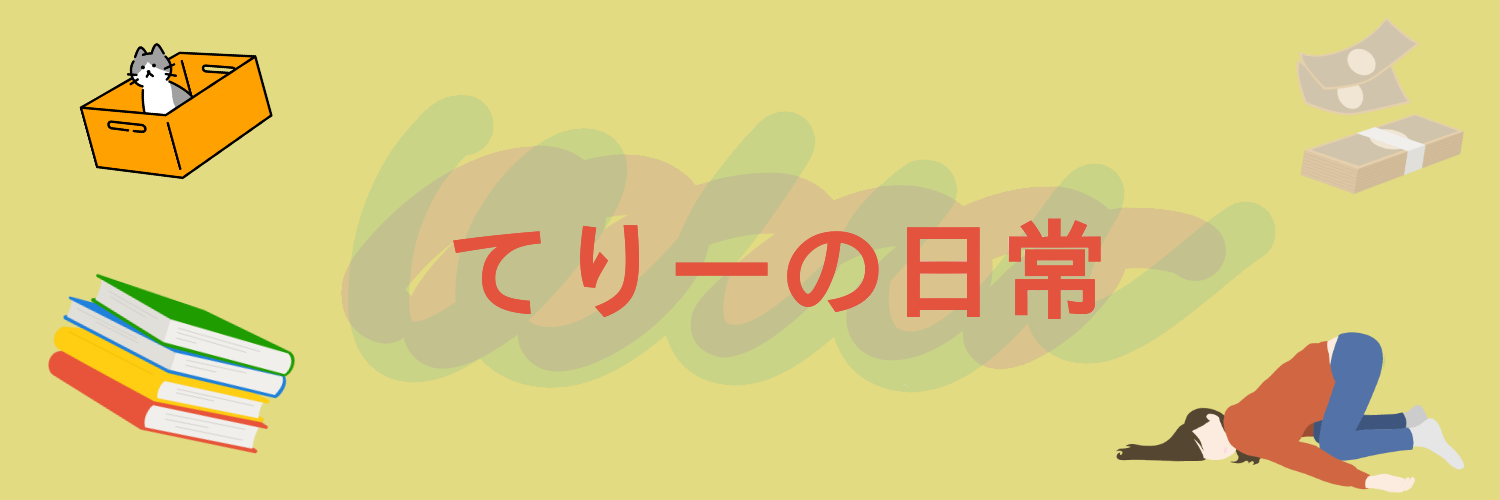






コメント